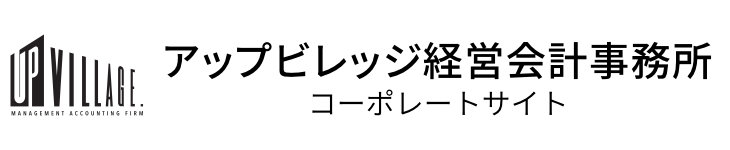今回は「消費税の納税義務と合併承継」について。
包括承継の新設合併、吸収合併事業譲渡と異なり、合併は、権利・義務の一切を承継する包括承継であり、自然人についての相続と同視されるところです。
包括承継の故に、課税主体間の財産の異動については、相続の場合と同じく、消費税法上の資産の譲渡から除かれます。
従って、法人税法における非適格合併であっても、この扱いに変わりありません。 合併には、新設合併と吸収合併があります。
新設合併では、2以上の会社が自らを消滅会社とし、新たな承継会社を設立します。
吸収合併では、1つだけが合併後存続する会社になり、他は合併により消滅する会社になります。
合併年における消費税納税義務合併年度おける被合併法人は合併により消滅法人になるので、課税期間が短くなるということはあっても、消費税の納税義務 に関しては特別な扱いはありません。
それに対して、合併法人については、扱いが異なります。
① 課税事業者である法人同士の合併
② 合併法人が課税事業者で被合併法人が免税事業者であるときの合併
③ 合併法人が免税事業者で被合併法人が課税事業者であるときの合併
④ 免税事業者である法人同士の合併、これら4ケースがあります
合併法人の課税・免税事業者判定は、
① ②のケースは年度を通じた課税事業者
② は合併当日からその年度末までの期間の課税事業者
③ は免税事業者です
合併翌年度では合併前各法人の合計で合併法人の合併翌事業年度の課税期間においては、合併法人の基準期間における課税売上高と被合併法人の対応基準期間の課税売上高の合計額で納税義務者の該当性を判定します。
新設合併の場合は、合併新設法人の基準期間はないので、被合併法人の対応基準期間の課税売上高しかありません。当然ながら、被合併法人の対応基準期間の課税売上高の合計のみで判定します。
なお、合併については、合併年度、合併翌年度に関する規定しかなく、翌々年度に係る規定はありません。
それは、翌々年度においては、合併法人の基準期間は存在するが、被合併法人の対応基準期間はすでに存在しないので、合計しようにも合計するものがないからです。
この記事の監修

-
税務調査専門の税理士
元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。
最新の投稿
- 2024年3月11日コラム採用成功の鍵を握る適性検査~導入メリットと選定のポイント~
- 2024年3月11日コラム採用ブランディングの全貌~企業成長のカギを握る戦略~
- 2024年3月11日コラム新時代の会計事務所選び~ワークライフバランスを実現するためのガイド~
- 2024年3月10日コラムフレックスタイムとリモートワークがもたらす税理士の新しい働き方